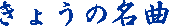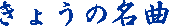【 ミサ「ス・ラ・ファス・エ・パル」】
デュファイ,ギョーム 〔ベルギー〕
(1397.08.05〜1474.11.27) 77歳
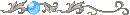
ルネサンス初期の最大の音楽家のデュファイは
中世からルネサンスへの時代の転換期に生きて、
なおかつその転換を自らの音楽で成し遂げた
十五世紀最大の音楽家である。
1400年頃、北フランスのカンプレ近郊で生まれたと
推定されていたが、最近の説ではブリュッセル近郊の
ベアセルで生まれたとされている。
カンプレ大聖堂の少年聖歌隊員として指導を
受けた後、1420年頃イタリアに出て、ローマ教皇
カペルラ、サヴォア公らの宮廷カペルラで活躍。
1450年頃にはブルゴーニュ公宮廷音楽家の
称号を得ている。
晩年にはカンプレ(現在のベルギーとフランスの
国境近く)に戻り、司教座聖堂参事会員をつとめ、
また多くの後進を指導して、550年前の
11月27日にこの地で没した。
シャンソン(フランス語の世俗的な歌詞による歌曲)
ミサ曲、モテットなどの多くの作品を残している。
中世後期のヨーロッパでは各国ごとに独自の音楽が
発達していた。
イギリスでは三和音を中心とした充実した和声法、
フランスでは、イソ・リズム法と呼ばれる方法を用いた
構成的な作曲法、またイタリアでは旋律優位の
音楽書法と、各国の音楽はそれぞれに個性的であり、
魅力的でもあったのだが、またそれぞれ弱い面も
持ち合わせていた。
しかし、ブルゴーニュ楽派の巨匠デュファイの
登場でそれらの諸々の手法は一つにまとめあげられ、
これによって、音楽の総合化・国際化への
道が開けることになった。
デュファイの次の世代のフランドル楽派の
音楽語法が全ヨーロッパ共通の基盤になりえたのも、
デュファイの業績といえ、彼の音楽は様々な意味で、
音楽におけるルネサンス時代の幕開けを
告げるものといえる。
そして、その音楽のルネサンス的な重要な
側面として、それまでの音楽には見られないほどの
人間的な表現意欲があげられる。
デュファイの代表作であるミサ「ス・ラ・フェス・
エ・パル」(私の顔が青ざめているのは)は、
グレオリア聖歌ではなく世俗歌曲を使用しながら、
あくまでも高貴に、かつ優雅でメランコリーな
表情さえとどめて鳴り響くミサ曲で、デュファイその人の
個性を強く刻みつけた音楽作品となっている。
|
|