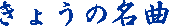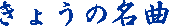【 管弦楽のための木挽歌 】
小山 清茂 〔日〕
(1914.01.15〜2009.06.06) 95歳
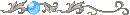
大正3年1月15日に元長野市で生まれた
小山清茂は、長野師範学校での音楽の授業で、
師のピアノを聴き、長野・東京で教職に
就いた後も音楽の研鑽を重ねた。
1945年に「管弦楽のための信濃囃子」が
第14回音楽コンクール作曲部門で
第1位に入賞し、その後代表作となる
「管弦楽のための木挽歌」(1957)など数々の
作品を発表、戦後を代表する作曲家としての
地位を築きあげた。
2009年(平成21年)95歳で世を去った。
中島敦と太宰治と松本清張が同年生まれである。
小山の作品からは、故郷長野の自然、素朴で
温和な人情味が感じられ、日本古来の伝統音楽や
民謡を用い西洋音楽として構築する手法は
独自の魅力を生み出している。
九州地方の民謡の木挽き歌を主題とした
「管弦楽のための木挽歌」は洒落っ気がありながら
決して「下品」に堕さず民衆の心からの喜びを
表現し尽くした変奏曲作品で、4つの部分からなる。
A : テーマ
B : 盆踊り
C : 朝のうた
D : フィナーレ
日本の全ての管弦楽曲を代表する名作で
代表作である『管弦楽のための木挽歌(こびきうた)」は
小学校の音楽の教科書に鑑賞教材として載っていて、
日本の初等教育を受けた者は誰しも
耳にした事のある、日本の管弦楽作品となっている。
この曲の人気は初演以来高まり、作曲者自身に
よって吹奏楽用にも編曲(1970)されていて、
吹奏楽版の演奏頻度の方が、その演奏人口の
裾野の広さを反映して、遥かに高い。

(管弦楽)NHK交響楽団
(指揮) 岩城宏之
♪ 私が聴いた音源 ♪
|
|