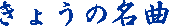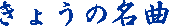【 歌劇「イーゴリー公」】
ボロディン,アレクサンドル
ポルフィリェヴィチ 〔露〕
(1833.11.12〜1887.02.27) 53歳
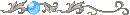
国民学派のロシア五人組のひとりのボロディンは、
ロシア貴族と軍人の娘との間に184年前の
11月12日にペテルブルクで、私生児として生まれた。
十九世紀前半までの音楽は、ドイツ、イタリア、
フランスが中心で発展し、その他の国々では
見るべきものがなかった。
十九世紀後半になると、それぞれの民族特有の
音楽を作ろうとする気運が高まり、
国民音楽の先駆となったのがロシアだった。
ボロディンが29歳のときに加わって出来たのが、
国民学派のロシア五人組(力強い仲間)である。
キュイ(1835〜1918)築城学の権威
バラキレフ(1837〜1910)数学専攻
ムソルグスキー(1839〜1881)
リムスキー=コルサコフ(1844〜1908)
しかし、ボロディンは有機化学の研究者であり、
医科大学の教授として多忙な生活を送っていたため、
「日曜日の作曲家」と言われていて、
一つの作品の完成までに長い年月を要した。
ロシア国民主義の歌劇として代表的なものであり、
ボロディンの作品のなかでも、彼の個性が
最も強く発揮されたものとして知られている
「イーゴリー公」は、彼が世を去ったときには
完成してなかった。
ボロディンの死後、リムスキー=コルサコフと
弟子のグラズノフが共同してまとめあげ、
オーケストレーションをし、まとまった歌劇に構成した。
序曲
プロローグ プティヴルの広場
第1幕 第1場ーガリツキー邸の庭
第2場ーヤロスラヴナの部屋
第2幕 ポロヴェッツの陣営、夕暮。
第3幕 ポロヴェッツの陣営
第4幕 プーティヴルの広場
今日では、歌劇の全曲が上演されることは稀で、
第2幕の「ポロヴェッツ人の陣営」の場面だけが
親しまれているが、管弦楽曲として演奏される
「ポロヴィッツの娘たちの踊り」は、この歌劇の
第2幕と第3幕に用いられた舞曲を、
ボロディンが演奏会用に編曲したものである。

歌劇「イーゴリー公」 - 序曲
(管弦楽) ロンドン交響楽団
(指揮) ゲオルク・ショルティ
♪ 私が聴いた音源 ♪
|
|