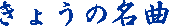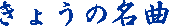【 交響曲 第4番 ニ短調 Op. 13 】
ドボルザーク,アントニン 〔チェコ〕
(1841.09.08〜1904.05.01) 62歳 脳溢血
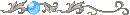
ドヴォルザークは交響曲を9曲書いた。
彼の生前、番号なしの2曲(第3、第4)と
第1番から第5番(第6、第7、第5、第8、第9)が
出版され、永眠後、後の2曲(第1、第2)が現れた。
第1番 ハ短調 作品3,B9「ズロニツェの鐘」(1865年)
第2番 変ロ長調 作品4,B12 (1865年)
第3番 変ホ長調 作品10,B34 (1873年)
第4番 ニ短調 作品13,B41 (1874年)
第5番 ヘ長調 作品76,B54 (1875年)
第6番 ニ長調 作品60,B112 (1880年)
第7番 ニ短調 作品70,B141 (1885年)
第8番 ト長調 作品88,B163 (1889年)
第9番 ホ短調 作品95,B178「新世界より」(1893年)
ドヴォルザークの作品には、作品番号のないものや、
作曲順になってないものが多いので、ブルグハウザーが
整理して付けた番号が「B.」で略記されることがあり、
「B番号」と呼ばれている。
1873年から75年にかけて第3番から第5番までの
3曲を毎年一曲ずつ相次いで作曲している。
それは、彼がオーストリア政府の奨学金の審査会に
提出する目的で書かれたものだった。
第3番では、リストやワーグナーの影響があり、
楽章構成も唯一3楽章の形だが、この作品で多額の
奨学金を得られ、審査員だったブラームスの支持を
得る契機ともなった。
第4番は4楽章構成に戻り、古典主義的な
構成的交響曲の延長戦上にある新しい創作を
意識したかのような構想をしめしていて、
ブラームスの影響が感じられる。
その後に書かれた交響曲においても、再びボヘミアの
民族的色彩を強めていることなど、次の作風への転換を
示唆してようである。
ドヴォルザークは、第4番を書いた前年の11月17日に
マリア・チェルマーコヴァーと結婚していて、
落ち着いた生活のなかで作曲活動をしていた。
1892年にアメリカに旅立つ前の告別演奏会で
初演されたが、その後も生前に出版されることはなかった。
第3楽章だけは、1874年5月25日にプラハで、
スメタナの指揮で演奏されている。
第1楽章 Allegro
第2楽章 Andante sostenuto e molto cantabile
第3楽章 Scherzo: Alleglo feroce
第4楽章 Finale: Allegro con brio

(管弦楽)ロイヤル・スコティッシュ管弦楽団
(指揮) ネーメ・ヤルヴィ
♪ 私が聴いた音源 ♪
|
|