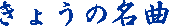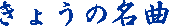【 弦楽四重奏のための三小品 】
ストラヴィンスキー,イーゴル 〔露〕
(1882.06.18〜1971.04.06) 88歳
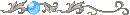
ストラヴィンスキーは、ペテルブルクの郊外の
オラニェンバウムで、著名なオペラ歌手の父と、
音楽の天分に恵まれていた母との間に生まれた。
家には20万余の蔵書があり、後に作品の素材となる
多くの民間伝承や、オペラのスコアが含まれていた。
9歳のときに両親はピアノの先生につけたが、
楽譜を読むことをたちまち覚え、
即興演奏をするようになったものの、
特別の天分は示さなかった。
父の勧めで、大学では法律を勉強したが、
学友にリムスキー・コルサコフの息子がいて、
本格的に作曲家になる決心をした。
しかし、その後も音楽学校には入らず、
法律を勉強しながら、リムスキー・コルサコフから
作曲法や管弦楽法を学んだ。
第一次大戦では、戦火を逃れて
母国ロシアを捨て、スイスに移住した。
さらに終戦後は、演奏の場を求めてフランスへ移り、
そこで、画家のピカソや作家のコクトーとの交流を
深めたが、この時期の作風は革新的なものから、
古典的な手法に変わった。
1938年、長女を結核で失い、翌年には
妻と母を相次いで病で失った。
第二次世界大戦から逃れることもあって、
ハーバード大学の招きで、単身アメリカに渡り移住した。
翌年、画家のヴェラと再婚し、新たな人生を歩き始めた。
二度の大戦で居住地を変えたが、作風も大きく変わり、
自分にとっての新たな音楽を追い続け、そこから
独自のものを作り続けていった。
その探究心は、死の直前まで衰えず、病床でも
作曲を続け、最愛の妻が見守るなか、49年前の
4月6日にニューヨークで88歳の生涯を閉じた。
彼は、社会的活動を全く好まず、音楽団体の
世話役や会長にも就任したことがなかった。
故国の革命にも無関心だったし、自身の創作を
妨げられることを避けた人生で、彼は長いあいだ
問題の作家だった。
1930年代頃まで、1作品毎に大胆な実験を行ない、
常に「変貌」を続けていった。
ストラヴィンスキーの初期の原始主義の傾向から
「新古典主義時代」へと移っていく中間の作品が
「弦楽四重奏のための三小品」である。
1914年、フランスのサルヴァン山中で
短時日の間に書き上げられたが、この曲は
その後の大きな作品の下準備となっている。
第1曲は、印象的なロシア民謡の旋律で始まり、
素朴な民謡調をねらった楽章。
第2曲の楽想は、後の「結婚」「兵士の話」
「ピアノ・ラグ・ミュージック」の中心的な
前触れとなっていて、 無調的な音の配列をみせている。
第3曲は「グランド・コラール」を思わすような
不協和なコラールである。
第1曲 Dance
第2曲 Eccentric
第3曲 Canticle

(演奏)オルフェウス室内管弦楽団のメンバー
♪ 私が聴いた音源 ♪
|
|