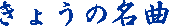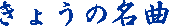【 弦楽四重奏曲 第1番 イ長調 】
ボロディン,アレクサンドル・
ポルフィリェヴィチ 〔露〕
(1833.11.12〜1887.02.27) 53歳
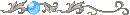
十九世紀前半までの音楽は、ドイツ、イタリア、
フランスが中心で発展し、その他の国々では
見るべきものがなかった。
十九世紀後半になると、それぞれの民族特有の
音楽を作ろうとする気運が高まり、国民音楽の
先駆となったのがロシアだった。
ボロディンが29歳のときに加わって出来たのが、
国民学派のロシア五人組(力強い仲間)である。
キュイ(1835〜1918)(築城学の権威)
バラキレフ(1837〜1910)(数学専攻)
ムソルグスキー(1839〜1881)
リムスキー=コルサコフ(1844〜1908)
しかし、ボロディンは有機化学の研究者であり、
医科大学の教授として多忙な生活を送っていたため、
「日曜日の作曲家」と言われていて、
一つの作品の完成までに長い年月を要し、
作られた音楽作品はきわめて少ない。
民族的特色を生かしたロシア国民学派の音楽は、
グリンカによって始まり「五人組」に引き継がれた。
当時、ロシア国民学派の仲間の関心は、歌劇や
標題音楽や歌曲にあって、室内楽などの抽象的な
純粋器楽にはあまり興味を示さなかった。
キュイは弦楽四重奏曲のことを、「音楽の退屈な種類」
と呼び、バラキレフはバッハのフーガでさえ
「挽臼が回っている」と評した。
そのなかにあってボロディンだけは、室内楽に
かなりの興味を示し、初期のピアノ五重奏曲の他に
弦楽四重奏曲を2曲残した。
化学者として活躍をしていたボロディンは、
一つの作品の完成までに長い年月を要したため、
1874年から書き始めた「弦楽四重奏曲第1番」の
完成には4年を費やした。
1880年12月30日にロシア音楽協会四重奏団により
初演された。
古典的なソナタの構成によって楽想を
展開していて4楽章からなる。
第1楽章 Moderato - Allegro
第2楽章 Andante con moto
第3楽章 Scherzo: Prestissimo
第4楽章 Andante- Allegro risoluto
ボロディンは1887年の感謝祭の週間の2月27日に、
友人と歌って踊って楽しんでいるとき、突然倒れた。
動脈瘤の破裂だったといわれている。
最後の交響曲となった「第3番イ短調」は未完に終わり、
グラズノフが補筆完成させた。

(演奏)ボロディン四重奏団
♪ 私が聴いた音源 ♪
|
|